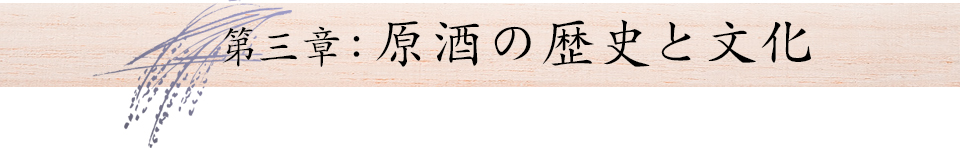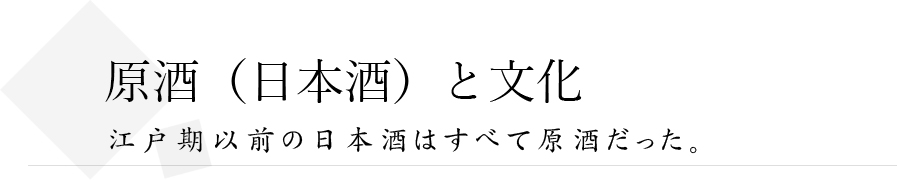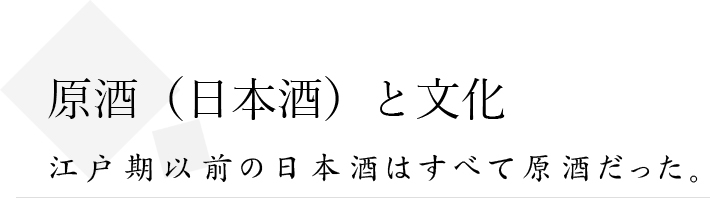日本酒の歴史は長く、そのルーツをたどれば、遠く大陸から稲作が渡来した弥生時代、九州から近畿地方にかけて始まった。
といっても、その形態はおよそ現在の日本酒とは遠くかけ離れている。それは、火を通した穀物を口に含んでよく噛み、唾液によ
って澱粉を糖化する「口噛酒」と言われるもので、この作業は巫女のみに許された神事の一つであった。
ちなみに、酒造りにおける「醸す」と言う言葉は、「噛む」が語源という説もある。
奈良時代になると「古事記」や「日本書紀」、「万葉集」、「風土記」など、さまざまな文献に酒と酒造の記述が登場している。そこでは「サケ」ではなく、「ミキ」「ミワ」「クシ」「キ」といった呼び方がされていた。
この時代の酒はアルコール発酵させた醪(もろみ)状のものを搾らず、飲み物というよりも、食べ物として箸などで食べられていた。
古事記には、百済から帰化した須須許里(すすこり)が、周の時代に考案された麹による酒造方法を、奈良時代初期に日本にもたらしたと記されている。これにより、米麹を用いた酒造りが普及していった。この時代には、須佐之男命(すさのおのみこと)が八俣呂知(やまたのおろち)を酒で酔わせて退治した有名な逸話があるが、その酒は出雲地方の「八塩折の酒」というもので、何度も繰り返し醸造した濃い酒であったという。
朝廷の酒から寺院の酒へ

大化の改新から平安初期の律令時代、酒は宮中に設けられた「造酒司」(みきのつかさ)で、四季折々につくられ、貴族たちの間で飲まれていた。
ここでは酒や酢の醸造を司っており、朝廷のための酒の醸造体制が整い、酒造技術が一段と進んでいった。当時の政治はまつりごとで、祖神をまつることにあった。まつりごとには酒が不可欠で、神祭りでは神々と共に酒を飲みあうことで、神の霊力が人々に伝えられた。当然ながら、庶民の口に入ることは希であった。
律令政治も終わりを迎える頃、「ハレの日」(特別な行事のある日)だけに飲まれていた酒が、「ケの日」(行事のない通常の日)にも飲まれるようになった。
これは、造酒司の酒造りの技術が民間に広まり、酒造りの中心が造酒司から日本各地の大寺院に移行したことによる。大寺院で造られた酒は「僧坊酒」と呼ばれ、遣隋使や遣唐使に加わった留学僧などの知識でさらに酒造技術が進化し、高野山の「天野酒」のように豊臣秀吉も愛飲した銘酒も誕生した。
僧坊酒によって大きな力をつけた各地の大寺院は、室町時代前期に全盛期を迎えた。
戦国時代に入ると、織田信長などの戦国武将達が大寺院の権力を恐れ、弾圧を加えるようになり、僧坊酒の歴史は幕を閉じ、酒造りは民間の造り酒屋へと移行していった。
造り酒屋による酒造りが広まった頃には、麹と蒸米と水を二回に分けて加える段仕込みなど、現在の酒造技術の原型が整っていった。
安土桃山時代から江戸時代にかけて日本経済の発展とともに酒の需要も増大し、時を同じくして大桶を作る技術が確立され、酒の生産量が飛躍的に増大していったのである。
江戸時代に入ると、一年を通して仕込んでいた酒造りが、「寒造り」へと移行していった。
冬期に仕込む寒造りは、低温・長期発酵で酒の風味が最も良くなる。
この変化により、夏は米作り、冬は酒造りに従事し、酒造りの全工程を取仕切る責任者である「杜氏」と、職人の「蔵人」という体制が生まれた。こうした経緯から次第に寒造りが主流となり、今日に至っている。
江戸時代の酒造りで特筆すべきは、アルコール度数と品質の向上である。
摂津(大阪府・兵庫県)の伊丹、池田、鴻池などで大桶を用いた三段仕込みによる酒造りが始まった。かつて2〜3石の容量の甕(かめ)や桶で仕込んでいたため、10斗程度しか仕込めなかったものが、20石の大桶によって仕込みの量が12石を超え、10倍以上の大量仕込みが可能になった。
さらに、寒仕込みに徹した低温・長期発酵と、掛け米の量を徐々に増やしていく三段仕込み、蒸米に対する麹の割合の調整などにより、アルコール度数が高く、格段に品質が良い酒が生まれた。
甘みが強く重い感じの味だった酒が、酸と甘みのバランスがとれたすっきりとした喉ごしとなった。
この摂津の酒は、酒の最大の消費地である江戸に送られ、江戸では「丹醸」と呼ばれる銘酒として人気を博した。
白く濁っていた酒も現在のような澄んだ酒になり、保存性を高める火入れ法や、香味を整えながら腐敗を抑えて歩留まりを良くする焼酎の混和法(アルコール添加)など、画期的な処理技術が次々と開発されていった。
元禄11年(1698年)には、2万7千もの酒造場が全国にできていたという記録があり、江戸時代になって日本酒は、ようやく庶民の手が出る存在となった。
日本酒の悲劇
昭和に入り、さらにに技術革新が進んだ日本酒だが、その歴史は二つの悲劇によって大きく低迷した。
ひとつは、第二次世界大戦後の米不足による「三倍増醸酒」である。
米不足によって、これまでのように酒造りができなくなったため、日本酒を水で薄め、醸造アルコールなどを添加し、生産量を増やすという発想で出来た酒が三倍増醸酒で、味と香りをよくするために、糖類や酸(乳酸やコハク酸など)の添加物が加えられた。
米不足という事情に対処するため苦肉の策で生まれた三倍増醸酒だが、後の日本酒離れの一因となったことは否めない。
ふたつめの悲劇は、「明治政府による酒の増税」である。
政府の財源を増やすために、それまでの酒税制度を改定し、アルコール度数により酒税の課税額が決められた。
これにより、多くの蔵元がアルコール度数の高い原酒の製造を中止し、醪を搾った後に加水された。
その後、課税方法が見直され原酒も他の日本酒と同等の課税になったが、これにより多くの蔵元から原酒造りのノウハウが失われてしまった。
醪を搾った原酒に加水やアルコール添加をした日本酒が生まれたのは江戸期からという。
江戸期以前の日本酒はすべて原酒だった。神代から続く天皇も、平安の世を詠った貴族たちも、群雄割拠した戦国武将たちも、原酒を味わっていた。
江戸期以降は、加水された日本酒は生活に欠かせない飲み物として親しまれてきた。
「下らない」という言葉があるが、これは江戸期の「下らない酒」が語源であるとされている。天皇がいる京都から見て、江戸に行くことは下ることである。伏見や灘から江戸に送られた「下り酒」に対して、他の地方で造られた酒は「下らない酒」と呼ばれ一段低く見られていたことから、「下らない」という言葉が生まれたという。